『Papers, Please』は共産圏っぽい国で入国審査官として労働する一風変わったゲーム。
1980年代の共産主義国家の空気はジョージ・オーウェルの『1984年』の影響も見られます。
『1984年』を読んでみると、世界観以外にも共通する点が見つかって興味深いです。
『Papers, Please』の共産圏っぽい世界観は、ジョージ・オーウェルの小説『1984年』に影響を受けたとのことです。そんなわけで、読んでみました。
※本記事は『1984年』と『Papers, Please』の両方のネタバレをやや含みます。注意!
『Papers, Please』はアルストツカという架空の共産主義国家が舞台。
プレイヤーは国境検問所で入国審査官となり、パスポートその他の書類をチェックして入国の可否を審査していくゲームです。
国境検問所を訪れる人はさまざまで、ときにルールに従うことが”正しい”行為かどうか迷うこともあり、プレイヤー自身の葛藤を呼び起こすところがゲームの特徴で、おもしろいところでもあります。
以前書いたレビュー記事はこちら。
【Papers, Please】レビュー 退屈な労働の日々がプレイヤーの心に葛藤を呼び起こす入国審査ゲーム
公式サイト:Papers, Please
Steam:Steam:Papers, Please
Playism:Papers, Please
『1984年』は1949年に英国で刊行されたジョージ・オーウェルの小説。
今回読んだのはハヤカワepi文庫の新訳版です。恥ずかしながら初めて読みました。
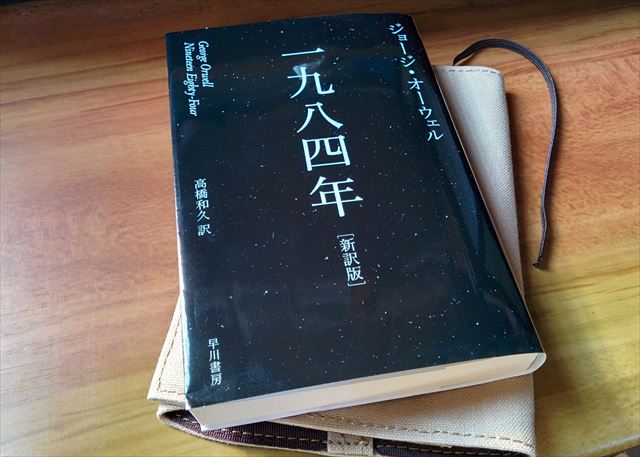
共産主義が統治した近未来世界を描いたディストピア小説です。
全体的に寒々とした重苦しい空気が漂い、物質的にも精神的にも厳しく統制された世界観で、もう共産主義というか、ファシズムをさらに一歩進めたような恐怖政治でしょうか。
執筆されたのが米ソの冷戦時代であるため、反共主義のバイブルとして扱われたのだとか。
『Papers, Please』の開発者のLucas Pope氏が『1984年』の影響を受けたというとおり、両者にはさまざまな共通点があります。単に世界観や雰囲気だけでなく、ゲームのコアとなる部分にも内包されているんじゃないかと思うのです。
世界観の共通点
どちらも1980年代の共産主義国家を舞台としているところは同じです。
『Papers, Please』では1982年の11~12月。
『1984年』はタイトルどおり1984年。といっても、”定かではない”のだけれど。
寒々とした重苦しい空気や閉塞感も共通しています。
物質的にも精神的にも自由がなく、貧困にあえぐところも同じ。
『Papers, Please』では国境検問所での労働とその日の収支報告を往復するだけですが、食費や暖房費を切り詰め、家族が空腹や体調不良に苦しむ、といったかたちで貧困が描写されています。働きぶり次第で給料が上がるっちゃ上がるんですけども。
『1984年』では貧困の描写は非常に多くなっています。
生活必需品は支給されるものだけなのに支給は少なく、支給品の質も最悪で、モノを買う自由もない、という徹底された全体統治ぶり。
全体統治といえば、『1984年』では「テレスクリーン」という双方向に投影されるテレビによって常に見張られているという描写もあります。職場にも街中にも自分の部屋にすら設置されており、監視社会ここに極まれり、って感じなわけです。
『Papers, Please』にそこまでの窮屈な社会システムはないですけど、審査を間違った瞬間に飛んでくる罰金の指摘なんかは、仕事ぶりを監視されているかのような錯覚を起こさせますよね。
名前オッケー…IDオッケー…身長体重オッケー…目的も滞在期間もオッケー…いいよな…?問題ないよな…? よし承認バチン!ようこそアルストツカへ!
………ガガガ…ガガガ…罰金5クレジット
この流れは何度やってもビクッとしてしまいます…。
隣人や家族ですら信用できない監視体制という意味では、『Papers, Please』でも秘密結社から受け取った大金を隣人にチクられる描写もあり、やはり自由のない世界という意味では近いものを感じますね。
Papers, Please – Trailer – YouTube
国家に対する不信感と反体制への誘い
『1984年』では、厳しい全体統制社会に疑問を抱く主人公ウィンストン・スミスが、ついにはルールを破って反体制側へいこうとします。その結果がどのようなことになるかもわかった上で、体制に反して自由を目指そうとするわけです。しかし、その結末はウィンストンの予想通りというか、予想以上の最悪の末路になってしまいます。
一方『Papers, Please』では、結末は1つではありません。
とはいえ、共通点はいろいろな点で見受けられます。
まず、国家に対する不信感を募らせるという点。
働いても働いても家族は貧しいままであったり、子供の絵を飾っているだけで罰金をとる上司であったり、目の前でテロ行為が頻繁に発生したりして、プレイヤーの心に徐々に徐々に不信感を積み上げていくわけです。
さらには、書類は足りないけど国に帰れば殺されると訴える人や、他国の報道陣をルールに則って退けるのが本当に正しいことなのかどうか、心を揺らがせ葛藤を呼び覚ますのです。日々変化する国際情勢に合わせてどんどん増える仕事のストレスも加わって不信感は増大する一方。
そんな折に現れるのが反体制の秘密結社EZIC。
不信感が肥大しているところなので、国家転覆を狙う組織が輝いてみえちゃうわけです。
国家に歯向かった者の末路
『1984年』でもブラザー同盟なる反体制の地下組織があり、ウィンストンも同盟に組み入ろうとしていますが、『Papers, Please』では秘密結社EZICに協力するかどうかはプレイヤー次第。
しかし、ウィンストンと同じく国家に反逆した場合に待っているのは厳しい結末です。
捕えられた後、ウィンストンが愛情省で受けた”再教育”のプロセスが待っているかどうかはわかりませんが、末路が終身刑か強制労働所送りとなれば、お先真っ暗であることは変わりません。
一応、家族を連れて亡命する結末もあるっちゃあるのですけども、黙って国家に従い続けるのが正解、というところは『1984年』と同じなんじゃないかなと思います。普通のゲームなら、いけすかない国家を転覆させるカタルシスをコアに設定しそうですし。
粛々と審査官の仕事をするゲームですから、ゲームのルールに従って正解を引き続ける結果が正解の結末、というのはゲームとしては何も間違ってはいないのですよね。
しかし、ゲームのルールに従うこと、つまりアルストツカに従うことが、果たして人間として”正しい”のかどうか、という葛藤が最後まで残ることになります。このあたりが『Papers, Please』を非常に印象的なゲームに押し上げている要因の1つなんじゃないかと思うわけです。
そんなわけで、『Papers, Please』をプレイした人は、ジョージ・オーウェルの『1984年』を読んでみるのもいいんじゃないでしょうか。ディストピア小説で作中ずーっと重くて暗い空気なので、耐えられる心を準備してから読むといいかも。
早川書房
売り上げランキング: 1,098